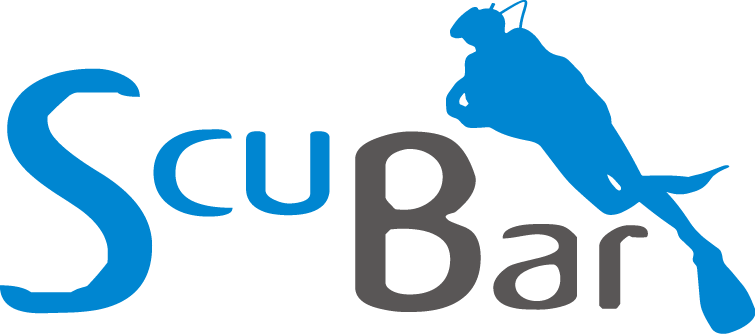旅の醍醐味の一つ。
『食べる』
本場の味を楽しむも良し、珍しいものを選ぶも良し。
ただ、その全てが口に合うという訳ではありません。
辛いものが苦手、香りが強いものが苦手。
日本食ではなかなか使われない食材のため、食べ慣れないものも。
好みはもちろんですが、冒険するには少し怖いものも多くあります。
主は『食事として食べるもの』であれば、焼いたレバーと煮込んだラム以外は何でもok。
お腹もありがたい事に、日常生活ですら困るほど頑丈、何でも美味しく食べていました。
そんな中で、『これは…』となってしまったものがいくつかあるのですが…
期待したものほど衝撃は大きく…
バックパッカーとして、旅中に一番気になることの一つに『値段』がある。
できるだけ出費を抑えて、少しでも余裕を持って旅を続けたい。
その中でも、毎日かかってしまう宿、そして食事。
安ければ安いほど良いのだが、もちろん何でも値段相応になってしまう。
主も、一日の予算内に抑えるため『こっちで贅沢をしたら、もう一方は我慢…』、『昨日出費が多かったから、今日は抑えて…』といったように旅を続けていた。
その点、タイやベトナム、インドネシアを始めとした東南アジアはありがたかった。
あれから10年以上経ち、倍以上に物価が上がった場所もある。
それでも、今でも一食200円ほどで食事ができる店も多い。
当時であれば100円あれば食べることができ、あまり値段を気にせずに注文できた。
そして何より、現地の人たちが行く店や屋台ですら、美味しい料理ばかりであった。
だからこそ現地の食堂でメシを食べることが、一つ楽しみになっていた。
それがそこの『美味いもの』だと思っていた。
のだが…
2011年8月 インド・ニューデリー
深夜に到着したホテルで一悶着あり、翌日の午前中に別の宿に移動した主。
その街、いや、その国での一食目、これがその旅の始まりだった。

場所が変われば全てが変わる。
コクがなく、ただ後味辛い
人がごった返しているニューデリー駅前。
食べもの屋が集まるエリアで昼食をとるため、値段と内容を吟味していた。
どの店も面白そうだったが、目についたのは寸胴でカレーらしき物を煮込んでいる店。
食べている人の様子を伺うと、プレートにスープが入った小さい器が2つ。
そして野菜を煮込んだものと、数枚のチャパティが乗っている。
聞くと40ルピー、当時で80円ほど。
おそらく観光客価格であったのだろう。
だが決して高いという値段ではないため、オーダーをして席についた。
写真を撮っていなかったため、画像が無いのが残念だが、見た目は決して悪くはない。
ターリーと呼ばれる料理の簡易版、といった印象だったのだが…
「あ、不味い…」
好き嫌いではない、不味かった。
たまたま出会い、一緒に食事をしていた日本人4人で思わず顔を見合わせた。
『出汁を取っていない味噌汁』と言えばイメージしやすいか。
ただただ辛いだけのスープ、深みやらコクが全くない。
安い店だからなのか、はたまた日本のインド料理屋が日本仕様に作っているだけなのか。
とにかく、色んな意味で衝撃であった。
この最初の食事がきっかけで、「インドの安飯屋は要注意」という記憶となった。
もちろん、その後に美味しいものが無かった訳では、決してない。
だがインドで食事の写真が無いのは、これが大きい理由である。

決して綺麗なレストランではないが、何でも美味い。
真実は9年後、突然明らかに
実は、これが前々回の最後に書いた『最近解けた謎』の一つ。
この話を、なんとなく来店した世界を旅したシェフ(=旅シェフ)に話をしたところ、
「おそらく『サンバル』というものではないか?」と言われました。
このサンバル(sambhar)という料理、もちろん米や生地と一緒に食べるそうですが、どちらかというと『ドレッシング』に近いものであるそう。
なので薄味、少し付けて味わう程度のものだそうで。
食事が美味しくなかったのではなく、『そういうもの』のようです。
9年もの間、さんざん不味いメシネタで使い、インドの人には申し訳ない…
とはいえ、味の上書きをしていない現在、不味かった記憶に変わりはないのですがね。
満を持して食すも…
ニューデリーの衝撃から2ヶ月後。
場所は変わり、スペイン・バルセロナ。
2日後に、カンプノウでの一戦を控えたこの地での食事といえば。

もちろん右の看板にしか目が行かなかった。
10ユーロ、当時で約1,250円。
1日30ユーロと決めていた中で安くはなかったのだが、レストランだともっと高い。
『ここは』と覚悟を決め、そして期待を多いに込めて入店した。
レジには少し年上であろう女性、そして後に外に出てくるシェフの男性。
夫婦で営んでいる様であった。
一番値段の安いパエリヤと、珍しくコーラをオーダー。
小さな店内にもいくつか席はあったが、せっかくならとサグラダファミリアを望む『テラス席』と呼ばる、ただ店の前の歩道にパラソルとテーブルを置いただけの席に着く。
喉が乾いていたのだが、少し調理に時間がかかるとのことで、ちびちびとコーラを啜っては、100年以上経っても未だ完成しない建造物を眺めていた。
そして約15分後。

例えピントが合っていなくとも…
珍しくちゃんと写真が残っていた。
それだけ期待が大きかったのだと思う。
『好きなものは最後に』な性格の主は、もちろん米の部分をまず食べる。
「…えっ…?」
何かの間違いだと思い、コーラで口を流しもう一口。
「いやいやいや…不味い…ってか、塩っ辛すぎる…」
「それに米に芯が残ったまんまやし…」
「調理を間違えたのか…それとも考えたくはないが、差別的な何かなのか…」
「そんなことより、全部食べ切れる気がしない…飲み物が足りん…」
道徳的にも金銭的にも残す訳にもいかず、なんとか食べ切った主。
そして会計のために店内に入ると、パエリヤを作ったシェフが一言。
「俺のパエリヤ、美味かったやろ!」(主意訳)
心からの笑顔でそう言われた。
そしてその横で微笑む奥さんであろう女性。
どうやら嫌がらせでは無かったようだ。
そんな二人に不味いとは言えるはずなどない。
「めっちゃ美味かった!」と誤魔化し、支払いのためにレシートを確認したのだが…
『あれ…なんか高い…』
あまり値段を確認するのもやらしいので、支払いを済ませ早々に退店。
角を曲がったところでもう一度確認すると、こうあった。
Paella € 9.50
Coke € 4.00
——————–
Amount €13.50
——————–
Service charge 10%
Terrace Seat 25%
——————–
Total €18.56
「テラス席って別料金やん!…しかも25%って…その値段でビール買えたやん!」
なんとも言えない気持ちになったのは言うまでもない。

25%取られても、この景色なら文句は言えない…のか?
料金はともかく、味は現地の味だった…?
このパエリヤなんですが。
先述のインドの食事と同じく、『最近解けた謎』の二つ目なんです。
インドの話をしたついでに、パエリヤが塩辛かった事を『旅シェフ』に聞いてみました。
すると、「それはそういう味であった可能性が高い。元々スペインやポルトガルの料理は塩気がかなり強いことが多い」とのことでした。
更に、「向こうで修行した人間も、日本でその料理を提供するにあたり、かなり塩気を抑えなければと考えるとも聞く」ともおっしゃっていました。
そしてもう一点。
以前、今や料理長のあのお方にふと、「リゾットとかパエリヤ食べたとき、芯が残ってることよくあるんやけど、なんでなん?」と聞いたことがありました。
もちろん、バルセロナで食べたパエリヤの記憶もあって、その質問になったのですが…
回答は、「いや、そういうもんやねん」とのこと。
もちろん、ちゃんとした理由を説明はしてもらいましたが。
そもそも『食材としての米』の概念が違うみたいなんです。
主食として米を食べる日本人と、一つの食材として調理する欧州とでもいいますか…
このあたりは本職の方にまかせるとして、『パエリヤの米に芯が残っていた』のは、『残っているのが普通』というものらしいです。
その土地、習慣、文化によって、本当に色々と変わるものです。
自慢の料理だと言っても、「植物の根っこなんか食べさせられた!」と言われたり、
体にもいいからと言っても、「腐った豆を出された!」とか言われたり。
日本に訪れる外国人も似たような経験をしているのかな?と考えたら、ちゃんと伝えてあげなければとも思います。
ちゃんと勉強し、理解してから食べるべきなのか。
食べた後、何故こんな料理なのかと調べるべきなのか。
ただただ、知らないものを知った衝撃を楽しむべきなのか。
まあどれであっても、美味いよりも不味いのほうが断然ネタにしやすいんですがね。